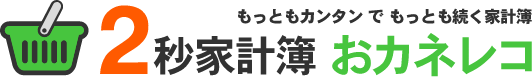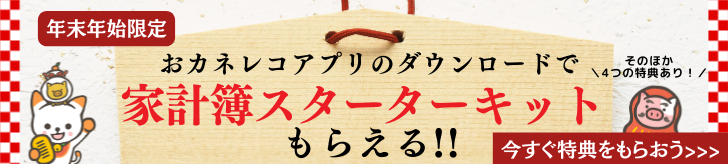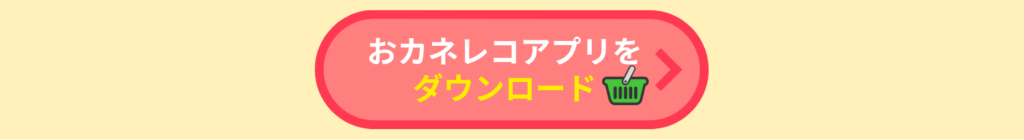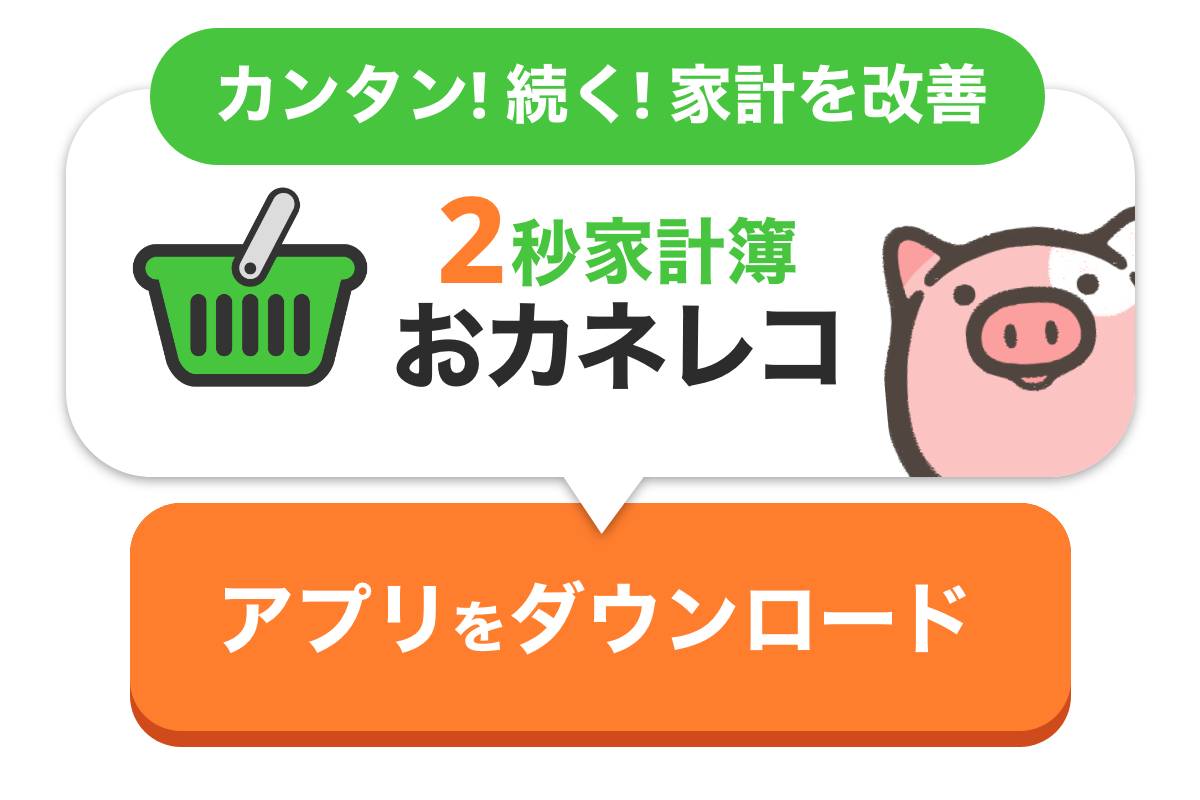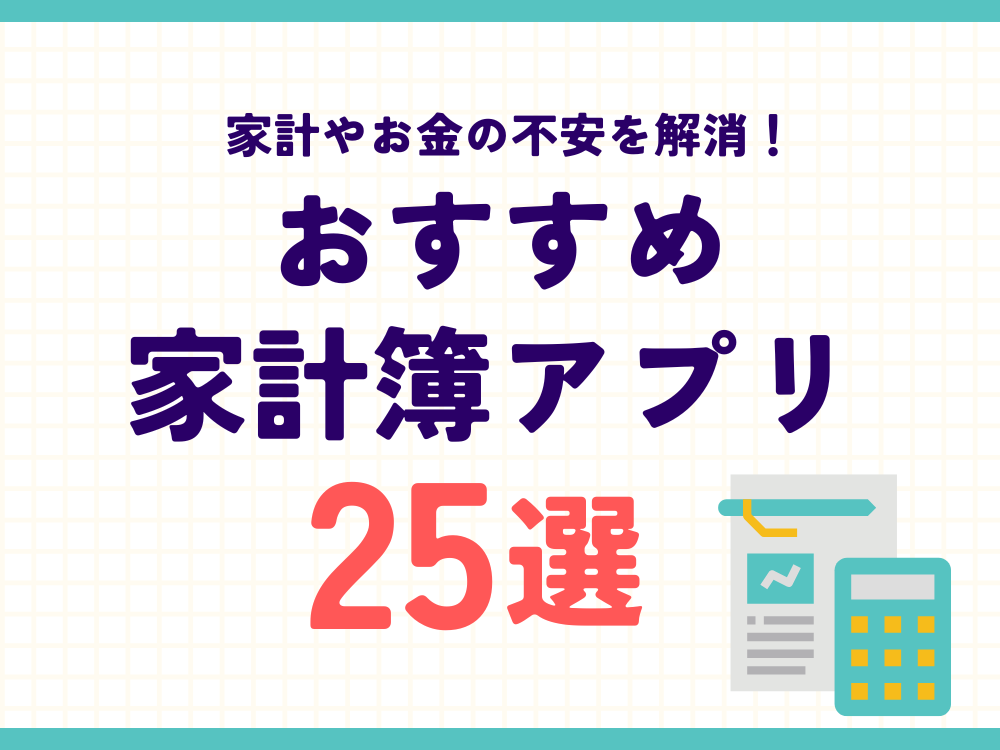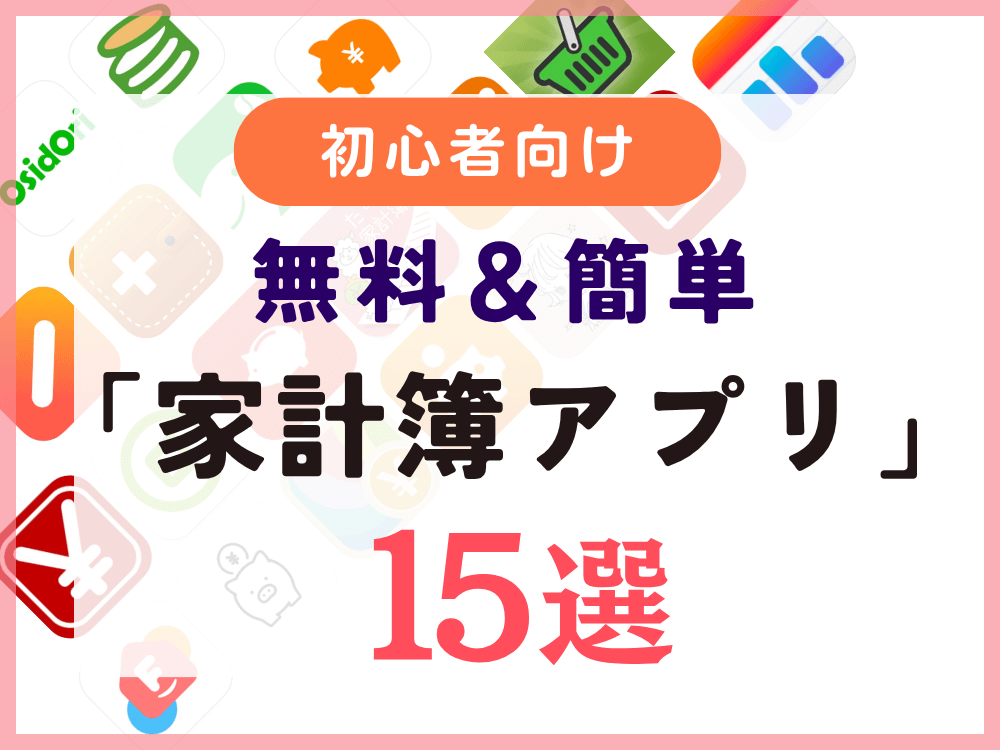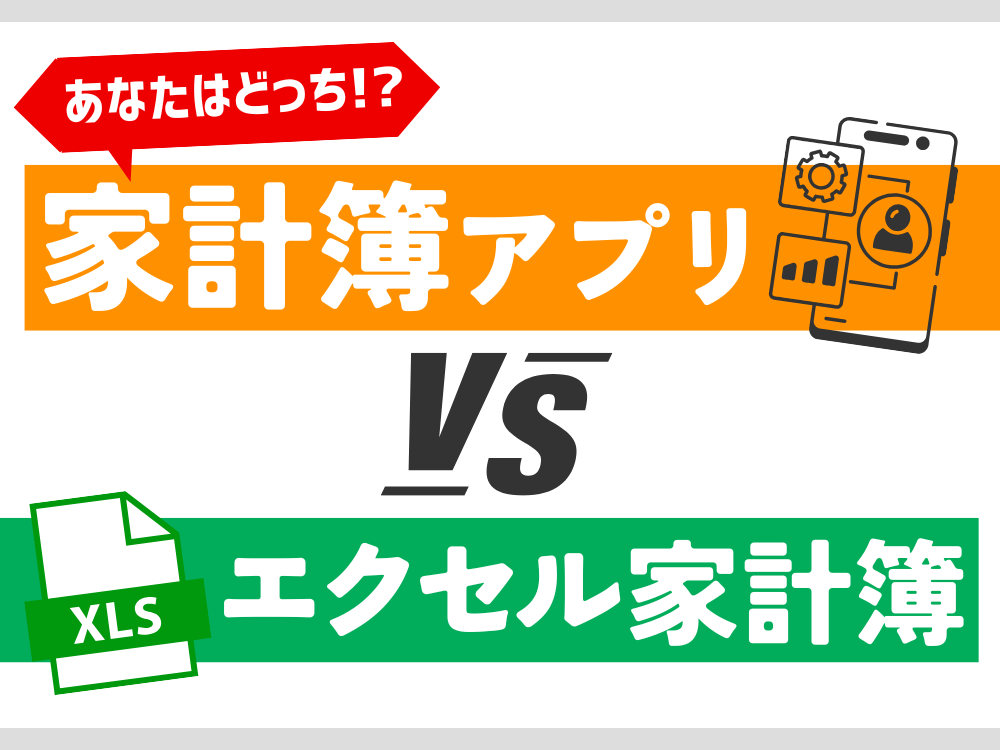家計簿をつける方法には、スマホアプリやエクセルなどのデジタルツールもありますが、昔ながらの「手書き家計簿」には独自の魅力があります。手を動かして書くことで支出の意識が高まり、お金の流れを実感しやすくなるのが大きなメリットです。
また、手書きなら自分の好きなレイアウトで記録できるため、必要な項目だけをシンプルにまとめたり、イラストや色分けで見やすく工夫したりすることができます。書くことで記憶に残りやすく、無駄遣いの傾向にも気づきやすくなるでしょう。
さらに、デジタルツールに比べて「書く習慣」を通じて家計を振り返る時間が増えるため、計画的なお金の使い方を身につけやすいのも魅力のひとつです。
「家計簿は続けるのが大変そう」と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、手書きなら自分のペースで気軽に始められます。
本記事では、初心者でも無理なく続けられる手書き家計簿のつけ方や魅力について詳しく解説していきます。
・手書きの家計簿に興味を持っている人
・どんな家計簿をつけようか悩んでいる人
すぐに家計簿始めるならこちらがおすすめ!
↓↓↓
目次
初心者でもできる!手書き家計簿の5つの基本ステップ
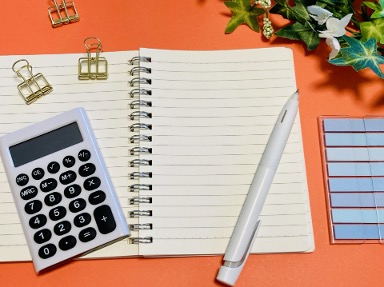
家計簿をつけるのは難しそう…と思う人もいるかもしれませんが、実はとてもシンプルな作業です。ここでは、初心者でも無理なく続けられる手書き家計簿の基本ステップを紹介します。
ステップ1:家計簿をつける目的を決める
最初に「なぜ家計簿をつけたいのか」を明確にしましょう。 「毎月の支出を把握したい。」「貯金を増やしたい 。」「無駄遣いを減らしたい。」など目的がはっきりすると、モチベーションを維持しやすくなります。
ステップ2:必要な道具を準備する
手書き家計簿を始めるために、次のような道具を用意しましょう。
・ノートやルーズリーフ(自分の書きやすいもので大丈夫です)
→シンプルなノートでもOKですが、家計簿専用のノートを用意すると習慣化しやすくなります。
・ペンやカラーペン(支出を色分けすると見やすいです)
・定規(表を作るときに便利です)
ステップ3 家計簿のフォーマットを決める
手書き家計簿にはさまざまなフォーマットがありますが、初心者には次の3つのどれかがおすすめです。
①シンプルな収支記録型(日付・支出・収入・残高を記録します)
②カテゴリー別管理型(食費・日用品・娯楽費など費目ごとに記録します)
③週・月単位でまとめるタイプ(毎日の記録が負担なら、週ごとや月ごとにまとめます)
自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
ステップ4:実際に記録してみる
ここからは家計簿をつけてみましょう!
・毎日の支出・収入を記録(使った金額と何に使ったかを書く)
・週や月ごとに振り返る(使いすぎた項目はないか確認)
・改善点を考える(節約できそうなポイントを見つける)
「全部しっかりつけなければ」と気負わず、まずは続けることを意識しましょう。
ステップ5:習慣化のコツを知る
家計簿を続けるためには、「無理なくできる工夫」が大切です。
<無理なくできる工夫案>
・1日5分だけ記録する習慣をつける
・まとめて記録する日を決める(毎週日曜日など)
・カラーペンやシールを使って楽しく記入する
最初は簡単な記録から始め、少しずつ慣れていきましょう。
この基本ステップを押さえれば、初心者でも楽しく家計簿を続けられます。次の章では、具体的な手書き家計簿のフォーマット例を紹介します!
おすすめの手書き家計簿フォーマット3選
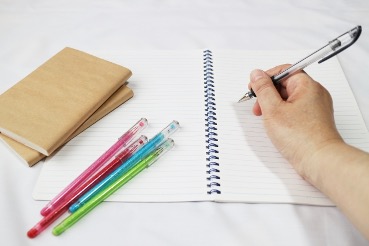
手書き家計簿を続けるためには、自分に合ったフォーマットを選ぶことが大切です。ここでは、初心者でも取り組みやすい3つのフォーマットを紹介します。
おすすめ①:シンプルな収支記録型(基本スタイル)
おすすめの人:家計簿初心者・シンプルに管理したい人
最も基本的なフォーマットで、日付ごとに「収入」「支出」「残高」を記録するだけのシンプルな形です。細かく分類する必要がないため、家計簿を続けるハードルが低くなります。
<書き方の例>
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 0円 | 3,500円 (食費) | 96,500円 | スーパーで買い物 |
| 2/2 | 50,000円 (給料) | 8,000円 (家賃) | 138,500円 | 家賃振込完了 |
<ポイント>
・とにかく簡単に書きたい人におすすめ
・1日5分で記録できるので、忙しい人でも続けやすい
・「メモ」欄を活用すると支出の振り返りがしやすい
おすすめ②:カテゴリー別管理型(費目別に把握できるスタイル)
おすすめの人:食費や日用品など、何に使っているか把握したい人
支出を「食費」「日用品」「交際費」「固定費」などのカテゴリーに分けて記録する方法です。どの項目にお金を使いすぎているかが一目でわかるので、節約しやすくなります。
<書き方の例>
| 日付 | 食費 | 日用品 | 交際費 | 固定費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3,500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 4000円 |
| 2/2 | 2,000円 | 0円 | 3,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
<ポイント>
・何にいくら使ったのかが明確になる
・節約ポイントを見つけやすい
・表を作る手間はかかるが、習慣化すれば便利
おすすめ③:週・月単位でまとめるタイプ(ざっくり管理スタイル)
おすすめの人:細かく記録するのが苦手な人・忙しくて毎日つけられない人
毎日の記録が負担になる場合は、1週間または1か月ごとにまとめて記録する方法がおすすめです。大まかな収支の流れを把握できればOKという人向けのスタイルです。
<書き方の例(週ごと)>
| 週 | 収入 | 支出 (合計) | 食費 | 日用品 | 交際費 | その他 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 50,000円 | 20,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
| 第2週 | 0円 | 15,000円 | 7,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 15,000円 |
<ポイント>
・細かく書くのが苦手な人におすすめ
・大まかな支出の傾向がわかる
・時間がない人でも無理なく続けられる
どのフォーマットが合うかは、人によって異なります。
・細かく記録するのが好きな人 → カテゴリー別管理型
・とにかく簡単に続けたい人 → シンプルな収支記録型
・忙しくて毎日記録できない → 週・月単位まとめ型
最初は無理なくできる方法を選び、慣れてきたら自分に合うようにアレンジしていくのもおすすめです。次の章では、実際に手書き家計簿のつけ方を詳しく解説します!
手書き家計簿の書き方3ステップ
ここからは、実際に手書き家計簿をつける方法を詳しく解説します。基本の流れを押さえれば、誰でも簡単に記録できます。最初はシンプルな方法から始めて、慣れてきたら自分なりにアレンジしていきましょう!
ステップ1:収入を記録する
家計簿をつける際、まずは「収入」を記録します。 収入には、以下のようなものがあります。
・給与・アルバイト代
・ボーナス
・副業収入
・臨時収入(お祝い・お小遣い など)
<記録のポイント>
・手取り金額(税引き後)を記入する
・収入を受け取った日ごとに書く
・副収入や臨時収入も忘れず記録
<記録の例(収入の記入)>
| 日付 | 収入の内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2/1 | 給与(手取り) | 200,000円 |
| 2/10 | フリマアプリ売上 | 5,000円 |
| 2/25 | ボーナス | 50,000円 |
ステップ2: 支出を記録する
次に「支出」を記録していきます。支出は、毎日こまめに記録するのが理想ですが、週や月単位でまとめてもOKです。支出は「固定費」と「変動費」に分けると、管理しやすくなります。
<固定費(毎月決まった額を支払うもの) >
・家賃
・光熱費
・通信費(スマホ・Wi-Fi など)
・保険料
・サブスク料金(Netflix・YouTube Premium など)
<変動費(毎月変動する支出)>
・食費
・日用品
・交際費
・娯楽費
・交通費
<記録の例(支出の記入)>
| 日付 | 支出の内容 | カテゴリー | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | スーパーで買い物 | 食費 | 3,500円 |
| 2/3 | 家賃 | 固定費 | 50,000円 |
| 2/5 | 友人とランチ | 交際費 | 2,000円 |
< 記録のポイント>
・使ったお金をその日のうちに記録する
・レシートを活用すると漏れが防げる
・色分けやマーカーを使うと見やすくなる
ステップ3:振り返りを毎月行う
1か月分の収入と支出を記録したら、最後に振り返りを行いましょう。
①収入と支出のバランスをチェック
「今月の収入と支出の合計は?」 「全体で見て赤字になっていないか?」
②支出の内訳を確認
「どのカテゴリーの支出が多いか?」 「無駄遣いはなかった?」
③翌月の予算を決める
「来月は○○円までに抑えよう」 「節約できそうなポイントはどこか?」
<記録例(1か月のまとめ)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入合計 | 250,000円 |
| 支出合計 | 180,000円 |
| 残高(収支合計) | 70,000円 |
| 貯金額 | 50,000円 |
<振り返りのポイント>
・予算オーバーした項目を見直す
・節約の目標を立てる(例:外食を月3回までに抑える)
・続けやすい工夫を取り入れる(週ごとの予算を決める など)
家計簿をつけることは、お金の流れを「見える化」し、無駄遣いを減らす第一歩です。「完璧につけよう!」と思うと続けるのが大変なので、まずは気軽に始めてみることが大切です。
家計簿を続けるための5つのコツ
家計簿をつけ続けることは大切ですが、「最初はやる気があったのに、途中で挫折してしまった…」という人も少なくありません。そこで、無理なく家計簿を習慣化するためのコツを紹介します!
コツ①:毎日ではなく「まとめて記録」でもOK
「毎日書かないと意味がない」と思うと負担になりがちです。忙しい人は、週1回や月1回まとめて記録する方法でも問題ありません。
<おすすめの記録ペース>
・毎日5分(コツコツ派の人向け)
・週末にまとめて記録(忙しい人向け)
・月末にざっくり計算(最低限の管理でOKな人向け)
<ポイント>
・レシートを保管しておくと、後からまとめて記録しやすい
・スマホのメモやノートに仮の記録をしておくのもアリ
コツ②:「完璧」を求めず、ゆるく続ける
「細かく記録しないと意味がない」と思うと、負担になってしまいます。
<家計簿が続かない人にありがちなNG行動>
・毎日の支出を1円単位で厳密に記録しようとする
・数日つけ忘れると、やる気をなくしてしまう
・最初から複雑なフォーマットを使う
家計簿は「大まかにでも続けること」が大切です。たとえ記録を忘れた日があっても、気にせず翌日から再開すれば大丈夫です。
コツ③:自分に合った方法で楽しむ
「書くのが楽しい!」と思えると、家計簿を続けやすくなります。楽しみながら続けるアイデアは以下の通りです。
<楽しみながら続けるアイデア>
・カラーペンやシールを使ってデコレーションする
・好きなノートや手帳を家計簿にする
・イラストを描いたり、手書きのグラフを入れる
特に手帳や日記が好きな人は、カラフルにしたり、コメントを書き込んだりすると、続けやすくなります!
コツ④:「家計簿をつけるメリット」を実感する
家計簿を継続すると、以下のようなメリットがあります。
・お金の流れが見える化できる → 無駄遣いが減る
・貯金のペースがつかめる → 目標が立てやすくなる
・お金の使い方に自信が持てる → 「貯める&使う」バランスが取れる
家計簿をつけることで「節約できた!」「今月は黒字だった!」という達成感が得られれば、続けるモチベーションにつながります。
コツ⑤:挫折しそうなときは「ゆる家計簿」に切り替える
「もう家計簿をやめようかな…」と思ったら、簡単な方法に切り替えましょう!
<ゆる家計簿のアイデア>
・1日ごとの記録をやめて、1週間ごとの合計だけ書く
・支出の細かい項目を減らして「生活費」「固定費」くらいの大枠で管理する
・ざっくり「今月いくら残ったか」だけを記録する
手書き家計簿は自由度が高いので、自分が続けやすいスタイルを見つけることが大切です。
①〜⑤の内容をまとめると、家計簿を継続するためには、次のポイントを意識することが大切です。
・週1回・月1回の記録でもOK!
・完璧を求めず、気楽に続ける
・色やイラストを使って楽しむ
・家計簿のメリットを実感する
・挫折しそうなときは「ゆる家計簿」にする
家計簿は、自分のペースで続けることが何よりも大切です。次の章では、手書き家計簿のメリット・デメリットについて詳しく解説します!
手書き家計簿のメリット・デメリット
手書き家計簿には、スマホアプリやエクセルにはない良さがありますが、一方でデメリットもあります。ここでは、手書き家計簿のメリット・デメリットを整理し、自分に合っているかをチェックしてみましょう。
手書き家計簿のデメリット
最初に手書き家計簿のデメリットを説明します。大きく4つのデメリットがあります。
デメリット①:計算や集計が手間になる
手書き家計簿では、毎月の合計金額や支出の内訳を自分で計算する必要があります。アプリのように自動で集計してくれる機能がないため、計算が面倒に感じることも。
<対策方法>
・電卓を使って簡単に計算する
・ざっくりとした管理にする(週・月ごとの支出合計だけ記録)
デメリット②:外出先での記録が難しい
外出中に買い物をしたとき、すぐに記録できないことがデメリットです。後からまとめて記録しようと思っても、忘れてしまうことも…。
<対策方法>
・レシートを取っておき、帰宅後にまとめて書く
・スマホのメモアプリを活用し、後で家計簿に記入
デメリット③:継続しないと効果が出にくい
手書き家計簿は、ある程度続けないとお金の流れがつかめません。「つけ忘れが増える → 家計簿が続かない」という悪循環に陥ることもあります。
<対策方法>
・週1回や月1回まとめて記録するスタイルにする
・書くのが負担にならないシンプルなフォーマットを使う
デメリット④:ノートがかさばる
1年分の家計簿をつけると、それなりに分厚くなります。保管スペースが必要になるため、長期間の管理には工夫が必要です。
<対策方法>
・必要な部分だけをまとめた「年間家計簿」を作る
・家計簿をスキャンしてデジタル化する
手書き家計簿のメリット
次に手書き家計簿のメリットを説明します。こちらも大きく4つのメリットがあります。
メリット①:書くことでお金の流れを意識しやすい
手を動かして書くことで、収支の流れを視覚的に把握しやすくなります。アプリで自動管理するよりも「自分で管理している実感」が湧き、無駄遣いに気づきやすくなります。
<こんな人におすすめ>
・しっかり家計を管理したい人
・お金の使い方を振り返る習慣をつけたい人
メリット②:自分好みにアレンジできる
手書きなら、フォーマットを自由にカスタマイズできます。
・シンプルに収支だけを記録する
・色分けやイラストを加えて楽しむ
・節約目標やメモを書き込む
アプリのような決まった入力項目に縛られないので、自分に合った形で家計管理ができます。
<こんな人におすすめ>
・自分のペースで書きたい
・手帳やノートを書くのが好き
メリット③ :スマホやPCがなくてもすぐ書ける
スマホやPCがなくても、紙とペンさえあればすぐに記録できます。デジタル機器が苦手な人や、シンプルな方法で管理したい人に向いています。
<こんな人におすすめ>
・スマホやアプリに頼りたくない
・シンプルな方法で家計管理したい
メリット④:データが消える心配がない
アプリやエクセルはデータが消えてしまうリスクがありますが、手書き家計簿ならその心配がありません。紙媒体なので、何年分もの家計簿を見返すこともできます。
<こんな人におすすめ>
・紙に書く習慣がある
・過去の家計データを見返したい
手書き家計簿が向いている人・向いていない人
手書き家計簿のメリット・デメリットを考慮すると、手書き家計簿が向いている人・向いていない人は以下の通りです
・書くことでお金の流れを意識したい人
・手帳やノートを書くのが好きな人
・外出先でもすぐに記録したい人
・スマホやPCで管理する方が楽な人
まとめ:手書き家計簿は自分に合った方法を見つけることが大切
手書き家計簿は、お金の流れを「見える化」し、支出の管理や節約を意識するための強力なツールです。アプリやエクセルと違い、自分のペースで自由に書けるという魅力があり、楽しみながら続けられるのがポイントです。
手書き家計簿には、メリットもデメリットもありますが、大切なのは 「自分に合った方法で家計管理を続けること」 です。
「手書きが向いている!」と思ったら → 気軽に始めてみる
「ちょっと大変かも…」と思ったら → アプリやエクセルと併用するのもアリ!
「お金を管理する力」は、一生使えるスキルです。手書き家計簿を活用して、自分のお金をしっかりコントロールできる生活を目指しましょう!
手書き家計簿が少し大変だと思ったら、エクセル家計簿や家計簿アプリを併用することもおすすめです。興味がある方は下記の記事もチェックしてみてください。
すぐに家計簿始めるならこちらがおすすめ!
↓↓↓