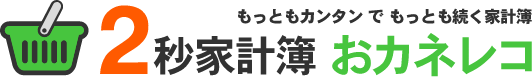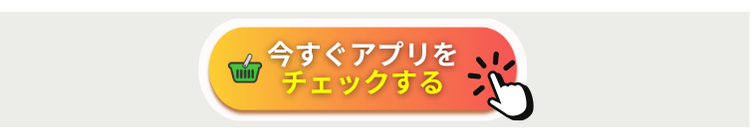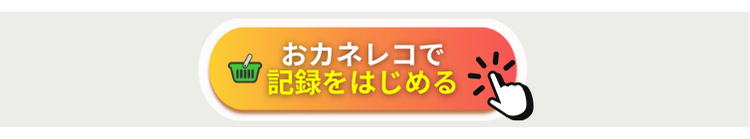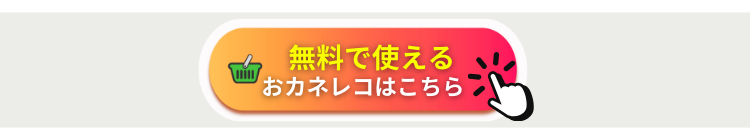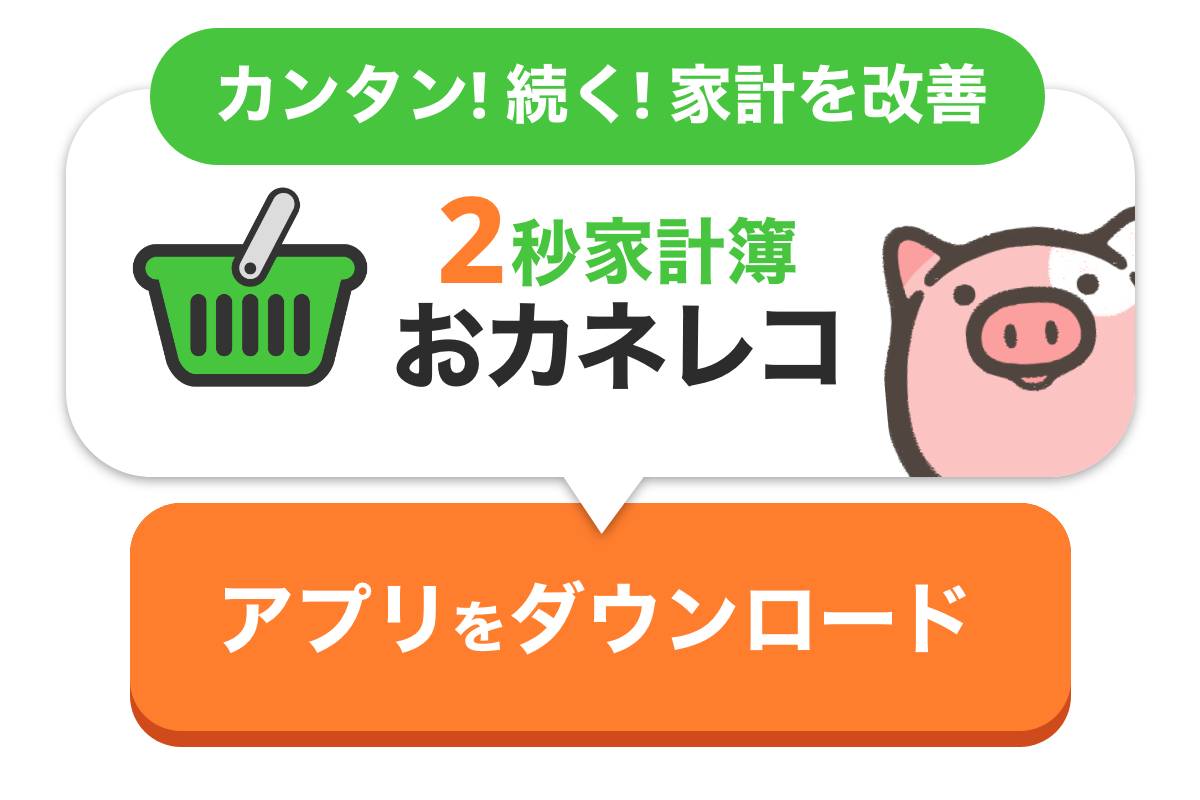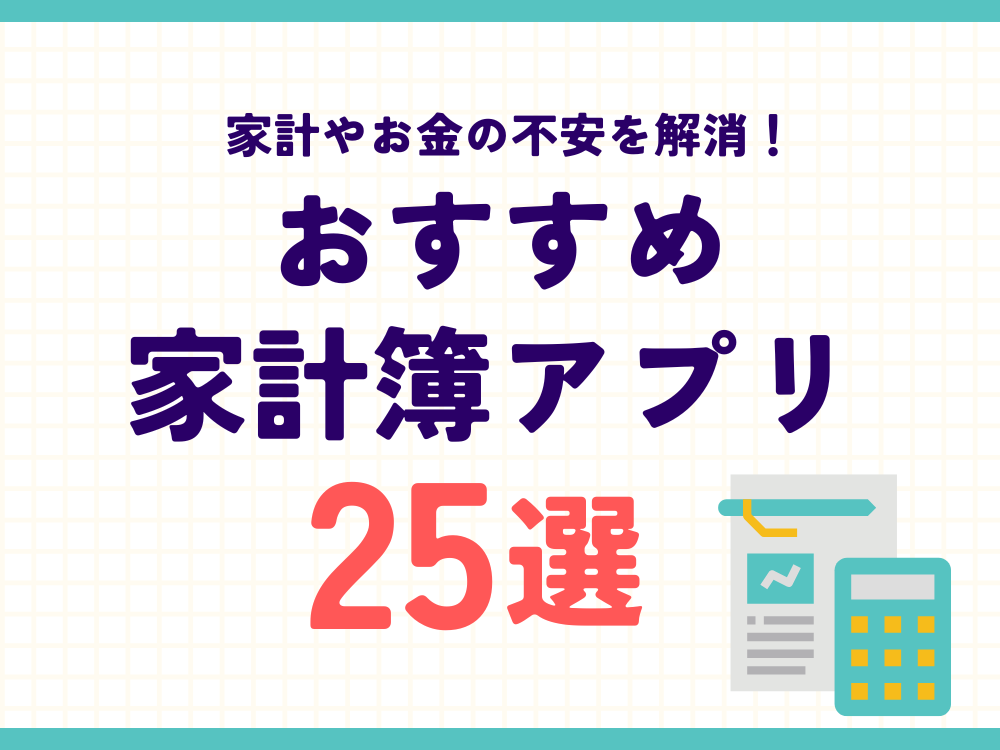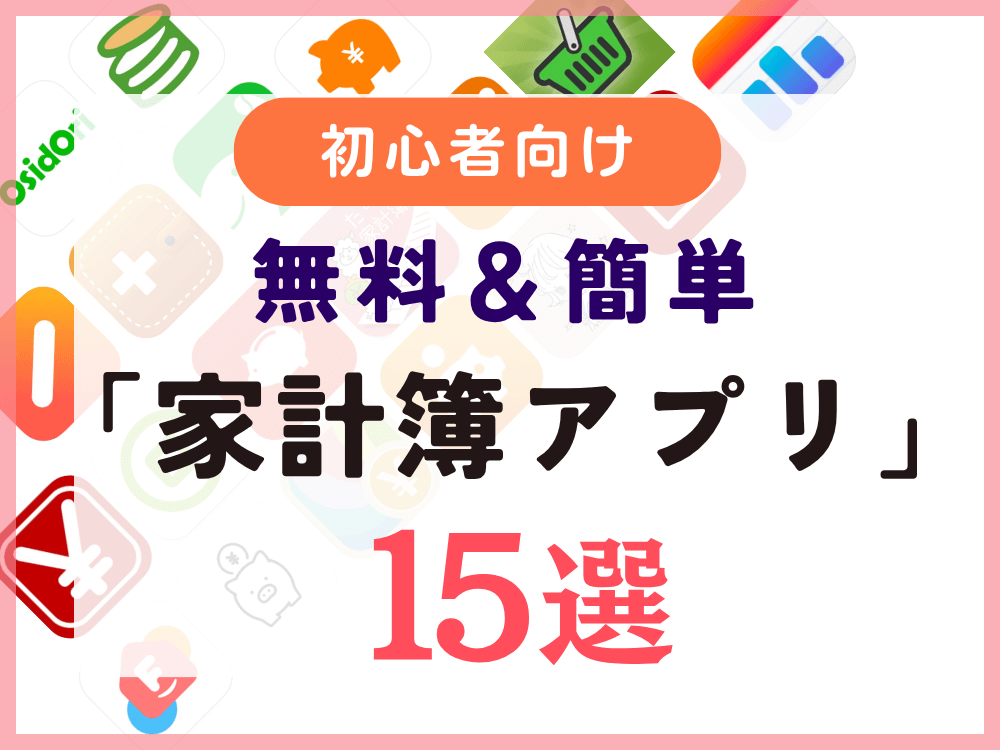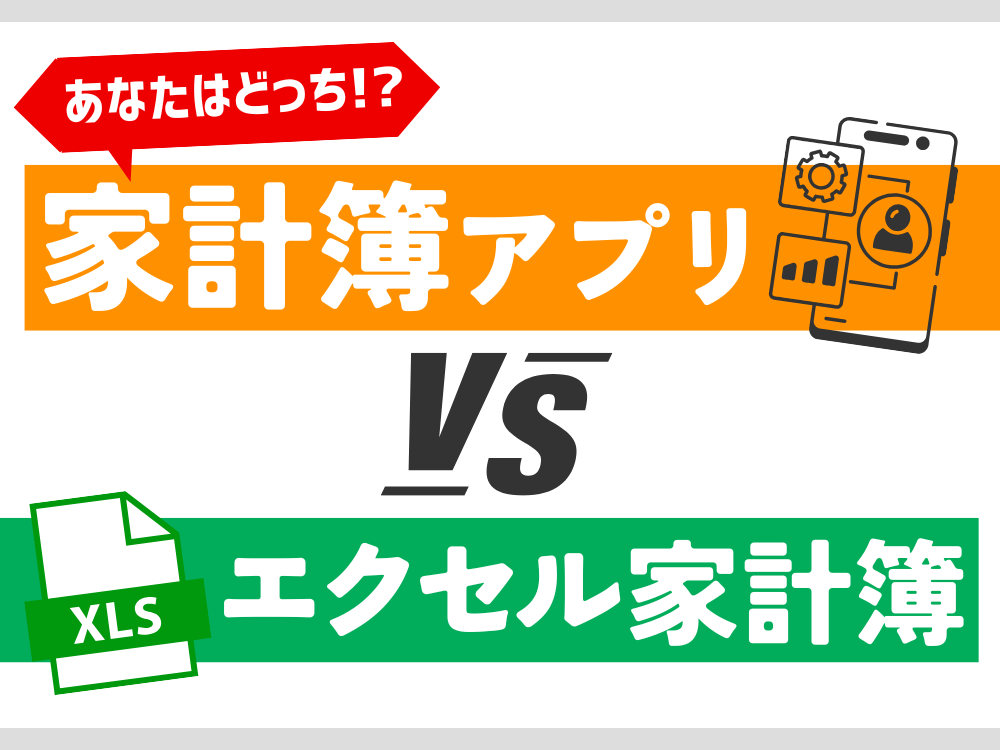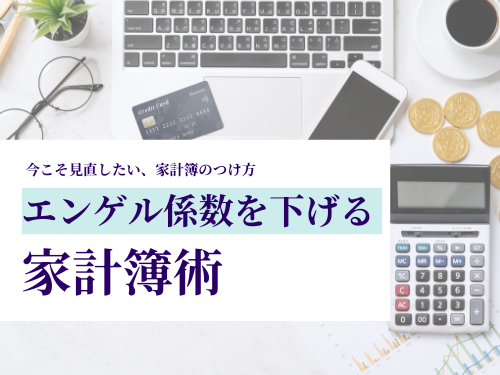
物価高で食費が家計を圧迫。家計簿のつけ方やエンゲル係数の意味をわかりやすく解説し、食費や固定費を無理なく節約する方法を紹介します。
目次
はじめに|食費高騰で家計を圧迫する今こそ見直しを
物価上昇や円安の影響で、「気づけば食費ばかりが膨らんでいる…」という声が増えています。
総務省のデータによると、2024年のエンゲル係数(消費支出に占める食費の割合)は43年ぶりの高水準となる28.3%に達しました。
これはつまり、収入に対して「食費が家計を圧迫している」状態が全国的に進行しているということです。
そんな今だからこそ、家計を立て直す第一歩として「家計簿」が注目されています。
収支を“見える化”するだけでなく、無理なく節約・貯蓄を進める強力な味方になってくれます。
この記事では、初めてでも続けやすい家計簿のつけ方から、エンゲル係数の意味、そして食費や固定費を見直す具体的な方法まで、わかりやすく解説します。
家計簿をつけるメリットと節約効果
「何に、いくら使っているか」がわかると、家計は驚くほど変わります。
つけてみて初めて、「あれ?こんなにコンビニで使ってた?」「なんとなく増えていたサブスク…」といった“気づき”が得られるのです。
家計簿は、節約や貯蓄のスタート地点。
見直すべき支出や、自分に合ったお金の使い方を発見するための「地図」のような役割を果たしてくれます。
家計簿の種類と選び方|続けやすい方法を見つけよう
最近は、金融機関やクレジットカード会社でも「家計簿アプリと連携した明細管理」を推奨しており、デジタル活用は今や主流の方法です。
特にスマホ世代や共働き家庭では、「とにかく続けやすさ」を重視する傾向があり、レシート読み取りや自動仕分け機能は圧倒的に便利。
アプリ型を活用することで、“頑張らなくても記録できる”安心感が得られます。
● 手書きノート型
- ノートや家計簿帳に自分で書く方式
- 書くことで意識づけがしやすく、自由度が高い
- 反面、手間がかかりやすく、継続が課題に
● アプリ型
- 家計簿アプリでスマホから簡単に記録
- レシート読み取り・自動カテゴリ分けなど便利機能が豊富
- おカネレコのようなアプリなら無料で始められるものも多く、初心者におすすめ
● クレジットカード・電子マネー連携型
- 利用明細を自動で家計簿に取り込める機能
- 入力の手間が減る一方、現金支出の管理には工夫が必要
💡 続けやすさで選ぶならアプリ家計簿!
おカネレコなら入力カンタン、無料ですぐ使える。
↓↓↓
家計簿が続かない人へ|完璧じゃなくて大丈夫
家計簿が三日坊主になりがちな理由は「完璧を目指しすぎること」。
毎日つけられなくても、週に一度まとめてでもOK。ざっくりでもOK。
例えば…
- 毎週日曜にレシートを見返して入力する
- 「食費だけ」「固定費だけ」などカテゴリを絞って記録する
- 支出合計だけを毎月残す“ざっくり家計簿”にしてみる
大切なのは「続けられる方法を見つけること」です。
家計簿で見えてくる“支出の偏り”
続けやすい形で家計簿を習慣化していくと、「実は食費ばかりが多かった」「外食が多い」「固定費が圧迫していた」など、自分では気づいていなかった傾向が見えてきます。
特に最近注目されているのが「食費の割合」。
食材の高騰や外食頻度の増加により、家計の中で“食費が重くのしかかる”という人が増えています。
そこで登場するのが「エンゲル係数」という考え方です。
エンゲル係数とは?平均値と計算方法を知ろう
エンゲル係数とは、「消費支出に占める食費の割合」のこと。
計算式:エンゲル係数(%)= 食費 ÷ 消費支出 × 100
この数値が高いほど、生活に占める食費の負担が大きいことを意味します。
2024年、日本の二人以上世帯のエンゲル係数は 28.3% と、1981年以来43年ぶりの高水準です。
背景には、以下のような要因があります:
- 食品の価格上昇(輸入コスト・円安の影響)
- 消費全体の抑制で相対的に食費割合が増加
- 外食・中食の利用増加
もともとエンゲル係数は、19世紀ドイツの経済学者エンゲルが提唱した「貧困層ほどエンゲル係数が高い」統計法則。
現代の日本では、「食費の中身をどう捉え直すか」が問われています。
エンゲル係数の推移:過去10年で何が変わった?
以下は、総務省「家計調査 家計収支編(二人以上の世帯)」に基づく、2014〜2024年のエンゲル係数推移です。
| 年度 | エンゲル係数(%) | 前年差(pt) |
|---|---|---|
| 2014 | 24.0 | — |
| 2015 | 25.0 | +1.0 |
| 2016 | 25.8 | +0.8 |
| 2017 | 25.7 | −0.1 |
| 2018 | 25.7 | ±0.0 |
| 2019 | 25.7 | ±0.0 |
| 2020 | 27.5 | +1.8 |
| 2021 | 27.2 | −0.3 |
| 2022 | 26.6 | −0.6 |
| 2023 | 27.8 | +1.2 |
| 2024 | 28.3 | +0.5 |
https://www.stat.go.jp/data/kakei/
📊 読み解きポイント
- 2014〜2019年はおおむね25〜26%台で横ばい。2016年は25.8%(前年から+0.8pt)。
- 2020年は27.5%へ大きく上昇(+1.8pt)。コロナ禍の消費構造変化の影響が色濃い年でした。
- 2021〜2022年はやや低下したものの、2023〜2024年は再び上昇。
2024年は28.3%と高水準です。
この推移を見ると、いま私たちが直面している“食費の重さ”が歴史的にも高水準であることがわかります。
食費を抑える具体的な節約方法
では、エンゲル係数を下げる=食費を見直すには、どうすればいいのでしょうか?家計簿を使ったシンプルな対策をご紹介します。
1. 食費カテゴリを細かく分ける
「食費」とひとまとめにせず、「外食」「スーパー」「コンビニ」「デリバリー」などに分けて記録してみましょう。
2. まとめ買いを“見直す”
特売だからと買いすぎてロス…を防ぐ。記録があれば、無駄も減らせます。
3. 外食頻度をチェック
「週何回外食してる?」を記録するだけでも意識が変わります。
「食費が高い=悪い」ではなく、暮らしに合った使い方を見つける視点が大切です。
🔍 家計簿をつけて、食費のムダを見える化しよう!
今日のレシートから、気づきが生まれるかも。
↓↓↓
固定費を見直して長期的に節約
家計簿を続けると、毎月固定で出ていくお金にも気づきやすくなります。
代表例:
- スマホ代(格安プランへの変更)
- サブスク(使ってない動画・音楽配信サービスの解約)
- 保険(今のライフスタイルに合っているか)
- 電気・ガス(契約プランの見直し)
一度見直すだけで、年間数万円の節約も。
「何もしていないのに毎月引き落とされている」支出こそ、チェックすべきポイントです。
家計簿が苦手な人は“見るだけ”からでもOK
「どうしても続かない…」という方は、記録よりも“見ること”から始めてみましょう。
- レシートをノートに貼って眺めるだけ
- クレジット明細を見て、今月の出費傾向を確認
- アプリで“円グラフ”だけ見る
おカネレコなら、記録の手間を最小限に、自動で振り返り通知も届きます。
📊 毎日の暮らしに“ちょうどいい”家計簿習慣を
スマホひとつで、家計が変わる。
↓↓↓
まとめ|家計簿とエンゲル係数で無理のない節約を
エンゲル係数が高騰する今だからこそ、自分の生活と向き合う時間を持つことが大切です。
家計簿は、ただ数字を並べるためのものではなく、「自分らしいお金の使い方」を探すヒントになります。
- 食費を見える化して、エンゲル係数を意識する
- 固定費の見直しで、じわじわ効く節約を
- 自分に合った方法で、まずは“ゆるく”始めてみる
おカネレコは、皆さんの“家計の見える化”をサポートします。
一緒に、家計を整える第一歩を踏み出してみませんか?